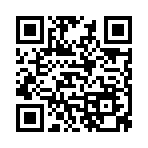2012年04月01日
藻類(そうるい)が熱い
藻類(そうるい)・・・・・ってようは水の中(湖水・海水)にすんでいる
植物プランクトンのことです。
最近、藻類の勉強・情報収集に余念がない。
藻類は顕微鏡でしか見れないような小さな植物プランクトンなんだけど、
藻類のうち油(オイルといってもいい)を作り出す品種があって
石油の代替ができるんじゃないかと期待が高まっているのだ。
数万種類ある藻類のうちオイルを作り出す種は数十種類なんだけど、
今のとこ有望なのは2種だけ。
ボトリオコッカス
オーランチオキトリウム
この2種、筑波大の渡辺 信 (わたなべ まこと)教授が中心となって
研究されているんだけど、TBSテレビ「夢の扉」でも紹介されていたから
見た人もいるはず。
ちなみにオーランチオキトリウムは渡辺教授が発見したものです。
2種ともオイル作り出す能力が高いんだけど、それぞれの特徴を
利点(+)、欠点(-)であげてみるよ。
ボトリオコッカス オーランチオキトリウム
・光合成する ・(+-)光合成しない
→「植物じゃないだろ」ってつっこまれそうだけど
実際、生物に分類されることもあり。
光の当たらない環境でも生産できる点は
プラスだが、
エサの有機物が必要になる点はマイナス。
・(+)オイルを細胞外に分泌する ・(-)オイルを体内に貯める
→死滅させずにオイルだけ取り →オイルを取り出すときすり潰して
出せる可能性あり。 死滅させるしかない。
・(-)増殖スピードが遅い ・(+)増殖スピードが速い
ということなんだけど、最後の増殖スピードは大量生産する上で重要なのは
言うまでもない。
オーランチオキトリウムの倍加時間(2倍になるのに必要な時間)は
水温10℃で12時間 20℃で4.2時間 30℃で2.1時間
と、かなり速い(エサさえあれば、すぐ増える)。
それに対しボトリオコッカスの倍加時間は7日~20日と、とてつもなく遅い。
「なんだ、ボトリオコッカスだめじゃん」と思うのはまだ早い!
最近、神戸大学の榎本 平(えのもと たいら)教授が1ケ月で1000倍以上
増える増殖スピードの速いボトリオコッカスの新株を発見したのだ。
これに榎本藻(えのもとも)と名付けたそうだ。
→ボトリオコッカスにもいろいろ種類があります。
う~ん、どちらも生かしたいなあ~。
渡辺教授も嘆いていたけど、国のかける予算が少なすぎるって。
アメリカは藻類研究・大量生産化に莫大なお金をかけているんだけど、
自分が政治家になったらかなりの予算をつけたい。
最後に藻類に関する今後の予定を書いときます。
・渡辺教授(筑波大学)・東北大学・仙台市が共同で
東日本大震災の津波で壊滅的な被害を受けた下水処理施設
「南蒲生浄化センター」(宮城野区)に集まる下水で、
藻類を増殖する実証実験を本年度内に始める予定です。
ようは1次処理で下水に含まれる有機物をオーランチオキトリウムの
エサにして、残りの水には窒素やリンが多量に含まれるのでそれを
栄養とするボトリオコッカスで2次処理をするそうです。
・榎本教授(神戸大学)が発見したボトリオコッカスの新株榎本藻を
使って、(株)IHIとベンチャー企業(有)G&GTが共同会社をつくり、
大量生産化を目指すそうです。
植物プランクトンのことです。
最近、藻類の勉強・情報収集に余念がない。
藻類は顕微鏡でしか見れないような小さな植物プランクトンなんだけど、
藻類のうち油(オイルといってもいい)を作り出す品種があって
石油の代替ができるんじゃないかと期待が高まっているのだ。
数万種類ある藻類のうちオイルを作り出す種は数十種類なんだけど、
今のとこ有望なのは2種だけ。
ボトリオコッカス
オーランチオキトリウム
この2種、筑波大の渡辺 信 (わたなべ まこと)教授が中心となって
研究されているんだけど、TBSテレビ「夢の扉」でも紹介されていたから
見た人もいるはず。
ちなみにオーランチオキトリウムは渡辺教授が発見したものです。
2種ともオイル作り出す能力が高いんだけど、それぞれの特徴を
利点(+)、欠点(-)であげてみるよ。
ボトリオコッカス オーランチオキトリウム
・光合成する ・(+-)光合成しない
→「植物じゃないだろ」ってつっこまれそうだけど
実際、生物に分類されることもあり。
光の当たらない環境でも生産できる点は
プラスだが、
エサの有機物が必要になる点はマイナス。
・(+)オイルを細胞外に分泌する ・(-)オイルを体内に貯める
→死滅させずにオイルだけ取り →オイルを取り出すときすり潰して
出せる可能性あり。 死滅させるしかない。
・(-)増殖スピードが遅い ・(+)増殖スピードが速い
ということなんだけど、最後の増殖スピードは大量生産する上で重要なのは
言うまでもない。
オーランチオキトリウムの倍加時間(2倍になるのに必要な時間)は
水温10℃で12時間 20℃で4.2時間 30℃で2.1時間
と、かなり速い(エサさえあれば、すぐ増える)。
それに対しボトリオコッカスの倍加時間は7日~20日と、とてつもなく遅い。
「なんだ、ボトリオコッカスだめじゃん」と思うのはまだ早い!
最近、神戸大学の榎本 平(えのもと たいら)教授が1ケ月で1000倍以上
増える増殖スピードの速いボトリオコッカスの新株を発見したのだ。
これに榎本藻(えのもとも)と名付けたそうだ。
→ボトリオコッカスにもいろいろ種類があります。
う~ん、どちらも生かしたいなあ~。
渡辺教授も嘆いていたけど、国のかける予算が少なすぎるって。
アメリカは藻類研究・大量生産化に莫大なお金をかけているんだけど、
自分が政治家になったらかなりの予算をつけたい。
最後に藻類に関する今後の予定を書いときます。
・渡辺教授(筑波大学)・東北大学・仙台市が共同で
東日本大震災の津波で壊滅的な被害を受けた下水処理施設
「南蒲生浄化センター」(宮城野区)に集まる下水で、
藻類を増殖する実証実験を本年度内に始める予定です。
ようは1次処理で下水に含まれる有機物をオーランチオキトリウムの
エサにして、残りの水には窒素やリンが多量に含まれるのでそれを
栄養とするボトリオコッカスで2次処理をするそうです。
・榎本教授(神戸大学)が発見したボトリオコッカスの新株榎本藻を
使って、(株)IHIとベンチャー企業(有)G&GTが共同会社をつくり、
大量生産化を目指すそうです。
Posted by 古恵良 元 (こえら はじめ) at 11:09│Comments(0)