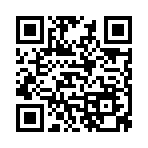2012年01月08日
教育は地域が決めるべき
きのう紹介した文章のなかで秀逸だと思ったのは
南里 俊策氏(大分合同新聞)の教育は地域で独自に行えるように
すべきという主張だった。
今の教育は文部科学省の役人が定める方針とは違うことはできないのだ。
私は日本が停滞しているのは、人材の多様性が失われてしまったのも
一つの原因だと考えている。
だからこそ地域が独自性を発揮できる地域単位・藩(はん)というものを
創設しようとしているのだ。
明治に近代が始まってから、欧米に追い付くこと主にして教育は
考えられてきたけど、(戦後も同じ)
欧米に追い付いた今日、それが完全に行き詰ってしまっている。
今の世の中は、どうすればいいかなんて誰もわからないし、
誰かが一律に決めたことが正しい保証は全然ない世の中なのだ。
(←霞が関の役人も含めて)
文部科学省の役人が教育方針を一律に決めるというやり方は
今の時代にふさわしくないものになっている。
そうだからこそ、教育は地域独自のものでいいと思っている。
多様な地域から生まれる多様な人材こそ
明日の日本をつくる大きな力となるであろう。
南里 俊策氏(大分合同新聞)の教育は地域で独自に行えるように
すべきという主張だった。
今の教育は文部科学省の役人が定める方針とは違うことはできないのだ。
私は日本が停滞しているのは、人材の多様性が失われてしまったのも
一つの原因だと考えている。
だからこそ地域が独自性を発揮できる地域単位・藩(はん)というものを
創設しようとしているのだ。
明治に近代が始まってから、欧米に追い付くこと主にして教育は
考えられてきたけど、(戦後も同じ)
欧米に追い付いた今日、それが完全に行き詰ってしまっている。
今の世の中は、どうすればいいかなんて誰もわからないし、
誰かが一律に決めたことが正しい保証は全然ない世の中なのだ。
(←霞が関の役人も含めて)
文部科学省の役人が教育方針を一律に決めるというやり方は
今の時代にふさわしくないものになっている。
そうだからこそ、教育は地域独自のものでいいと思っている。
多様な地域から生まれる多様な人材こそ
明日の日本をつくる大きな力となるであろう。
Posted by 古恵良 元 (こえら はじめ) at 05:59│Comments(0)