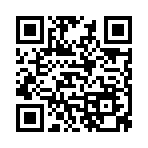2012年01月07日
廃県置藩
12月28日のブログで新地域創設が東北復興ならびに日本経済復活に
なるとして、「廃県置藩」(はいけんちはん)を唱えたんだけど、
自分の独自案のつもりでいたら、調べてみると他にも多くの人が提唱していたよ。
う~む、これらを参考にしつつ、責任党の方針をまとめねば。
榊原 英資(さかきばら えいすけ)氏のインタビュー記事より
{{道州制よりも江戸時代のような分権国家として完成した型の方がいいのではないか。
地方分権のモデルにしなくてはならないのは江戸時代的「藩」であろう。かれは、
明治4年の廃藩置県になぞらえて、廃県置藩と呼んでいます。
具体的には、300前後の基礎的自治体(藩)と国の二重構造にするというわけです。
地域の文化もほぼ藩を基準にして残っています。たしかに名産品として
丹後縮緬、加賀友禅などがあります。
したがって、国と藩のみで、市や村はなくした構造にしようというわけです。
これも一理あるのかも分かりません。
藩にせずに今の小選挙区単位でもいいかも分かりません。
首長や各議員は、自分の席がなくなるので、大反対するでしょうが、
現在の構造は、いずれにしろ無駄が多いことははっきりしていますので、
早急に改革に着手すべきでしょう。}}
関 良基(せき よしき)氏のブログより
{{江戸時代、ちょうど日本には300余の藩がありました。
江戸時代の日本は300の独立主権国家の連合体だったわけです。
加藤さんによれば「民主党は全国を300の広域連合自治体を
中心とした分権化を進める方針を出している」そうです。
これですとちょうど江戸時代の藩の数と同じになりますね。
私としては、なるべく旧藩の領域に合わせるように300にするのが
良いプランだと思います。地域の一体感という点で歴史的にもっとも
無理がない形だと思うのです。
最近の広域合併で、わけのわからない怪しげな地名も誕生していますが、
旧藩を復活させて、その名称に戻してしまうのが歴史的に無理がないように思えます。
もちろん加賀や薩摩や土佐のように、旧藩の大きさがちょうど現在の県の大きさに
等しいという地域もあるのですが、それはそれで良いのではないかと思います。
藩は自然の流域や地形に規定されたまとまりを単位としているので、
大きい藩もあれば小さい藩もあるのは仕方ないことです。
広い平野を擁する藩は大きくなってしまいますし、
小さい盆地や谷筋の藩は小さくなってしまいます。
しかし、それが自然の地形に規定された地域のまとまりだから仕方ない。
もちろん江戸時代の旧藩にも、幕府の策略で地理的にかなり
無理な線引きがされているものもありますから、
そうしたものはより自然のまとまりに修正する必要があります。
信濃の場合、江戸時代は11の小藩に分かれていました。
自然の地形に応じて盆地ごとに藩がある感じで、
盆地と盆地のあいだに山があってつながっていないので、
どうしても小藩に分かれざるを得なかったのです。
信濃では、最大が真田家・松代藩で10万石、
次いで松本藩の6万石、三番目が上田藩の5万3000石・・・・となります。
小さな藩ばかりでした。それぞれの盆地にそれだけの生産力しかないから
仕方なかったわけです。
そして今でも信州人は、盆地ごとに文化的な違いがあり、お互いに仲も悪いのです。
「道州制」というのは、私には何故必要なのかよく分かりません。
藩の上にくる統治単位は国でよいのであって、
道とか州とかいった名称の中間的統治単位が何故必要なのか疑問に思います。
もちろん藩と藩のあいだには大きさや工場の立地などに
応じて貧富の格差が生じるでしょうから、広域的に再分配を行う必要があります。
しかし、それは国がやればよいのであって、道とか州という単位は必要なのでしょうか。
道・州がどのような機能を果たすのか、イマイチよく分からないのです。
藩を自治の基礎として、さらに「信濃」というアルプスの山々に囲まれた地理的まとまりの
概念が共有されていればよいのではないかと私は思います。
道州制にあわせて「信濃」という概念が抹殺されてしまうような事態には私は断固として反対です。
加藤さんも、道州制の導入は新たな辺境を生み出すだけだと批判していましたが、同感です。
伊那谷の人々は、明治維新によって「長野県」という行政単位が導入されたことにより、
辺境の地位に押しやられてしまったという不満がかなりあるようです。
何せ、長野に行くよりも名古屋に行く方が早いという場所ですから。
しかし、伊那谷が名古屋圏に入ったとしても、
やはり名古屋圏の中の辺境として扱われるだけだし、
辺境として扱われる地域は今よりも増えてしまうだろう、というのが加藤さんの懸念でした。
私も同感です。
道や州は自治の基本単位としては大きすぎ、
「辺境」の地位で疎外された地域が多く出るでしょう。
藩の大きさならば、顔の見える範囲の自治が実現し、
誰もが主役になれ、地域は活性化すると思います。}}
植草一秀(うえくさ かずひで)氏のブログより
{{日本の国会議員数は、人口比で見ると、諸外国と比べて多すぎるものではない。
政府支出の削減という観点から見れば、削減するべきは国会議員定数ではなく、
地方議員定数である。
現在日本には1789の地方公共団体があり、
39,255人の議員定数と首長が存在する。
かつての3000団体から見れば約半分になったが、まだまだ多い。
日本の地方公共団体を、人口40万人を目安に300団体に再編し、
この300団体を基礎自治体とする。
基礎自治体には極めて強い自治権を付与する。
江戸時代の「藩」を復活させるわけだ。
つまり「廃県置藩」を断行するのだ。
この300の基礎自治体が20名定員の議会を持つなら、
議員定数と首長の合計は6300人になる。
各団体が30名定員の議会を持つなら合計数は9300人だ。
いずれにしても、現在の約4万人と比較すれば、4分の1ないし、
6分の1に人数を減らすことができる。
政府支出のスリム化を掲げるなら、この程度の抜本改革を行うべきだ}}
南里 俊策氏(大分合同新聞)のブログより
{{寺子屋、藩校、廃県置藩のすすめ
教育に力を入れたがために滅びてしまったという国が歴史上、
この地球にあったかどうか、その方面に疎い私には分からない。
ただ、十九世紀にアジアの国々が次々に欧米の植民地になる中で
日本だけはならなかった。
なぜか。その背景はいろいろあるが、その一つとして誰もが認めるのは
日本の教育水準の高さである。
例えば、識字率や就学率。江戸はそれが八割から九割に達していた。
同時代のヨーロッパ、もっとも進んでいたイギリスの都市で二割台、
フランスにいたっては一割にも到ってなかったという。
江戸の町は寺子屋だらけ、そこに六歳から八歳ぐらいの子が通って学んだ。
読み書き、そろばんの手習い、少し程度が高くなると、四書五経、漢詩の素読など
和漢の古典を叩き込んだ。
だれも「詰め込み教育反対」「ゆとり教育を」など気の利いたいた口を叩くものはいなかった。
強制、詰め込みこそが学力の原点であることを知っていたからである。
今の日本人はそこを勘違いしている。
こうした教育事情は地方でも同じである。
各藩は厳しい財政の中で藩校をたて、塾をつくった。
人材養成こそ苦境脱出の手がかりであると考えたからだ。
今のように「中央政府(幕府)はもっと教育予算を増やせ」と叫んでもビタ一文出るはずはない。
米百俵の精神で自分でやる以外にはない。
世界でもトップの日本の教育水準の高さは、こうした地域、地方の自立自存の素地の中から生まれた。
まさに地方分権である。
義務教育に反対するわけではないが、廃藩置県で教育は国の責任で行うものだと
みんなが考えるようになって,教育はおかしくなったのではないか。
全国画一的な教育ではなく、おれたちの町、あたしたちの村の子どもはこういうように育てたい、
そんなイメージを作ることだ。
町は貧しいけれど、何はともあれ教育だけにはカネを出そう、そんな町があってもいい。
またその反対の町もがあっても仕方ない。
住民が決めること。
年寄りは遅かれ早かれいずれ死ぬ。
町の明日、ひいては国の未来を担うのは子どもたち。
ひ弱な育て方をしてはいけない。
それには、読み書き、算数を徹底的に叩き込んで基礎学力作り。
あの藤原正彦先生も言っているではないか、一に国語、二に国語、三四がなくて五に算数と。
小学校ではこれだけやれば十分。
後はのびのびと体力作り。
うちの町の学校では、これ一本でやりますと、町長なり教育長が考えてもそれは出来ない。
霞ヶ関の役人たちが作ったこまごまとしたメニューウに従わなければならないからだ。
江戸時代に培われた地域の教育力を奪ったのは、廃藩置県による教育の国家統制である。
結論は出た。
教育の再生を図るには、廃藩置県を廃止し、新たな廃県置藩を断行、
地域の教育力を甦らせることだ。}}
荒木村重と名乗る人のブログより
{{廃藩置県からちょうど140年を経たの
中央集権が完全に制度疲労を起こしておる
そろそろ逆に回さねばならぬ
廃県置藩でもないが
人財も金財も権限も一極集中を止め
地域に分散せねばもうもたぬ
方言お祭り名物がどんどん溢れる
個性豊かな地方の地点を増やさねばならぬ}}
なるとして、「廃県置藩」(はいけんちはん)を唱えたんだけど、
自分の独自案のつもりでいたら、調べてみると他にも多くの人が提唱していたよ。
う~む、これらを参考にしつつ、責任党の方針をまとめねば。
榊原 英資(さかきばら えいすけ)氏のインタビュー記事より
{{道州制よりも江戸時代のような分権国家として完成した型の方がいいのではないか。
地方分権のモデルにしなくてはならないのは江戸時代的「藩」であろう。かれは、
明治4年の廃藩置県になぞらえて、廃県置藩と呼んでいます。
具体的には、300前後の基礎的自治体(藩)と国の二重構造にするというわけです。
地域の文化もほぼ藩を基準にして残っています。たしかに名産品として
丹後縮緬、加賀友禅などがあります。
したがって、国と藩のみで、市や村はなくした構造にしようというわけです。
これも一理あるのかも分かりません。
藩にせずに今の小選挙区単位でもいいかも分かりません。
首長や各議員は、自分の席がなくなるので、大反対するでしょうが、
現在の構造は、いずれにしろ無駄が多いことははっきりしていますので、
早急に改革に着手すべきでしょう。}}
関 良基(せき よしき)氏のブログより
{{江戸時代、ちょうど日本には300余の藩がありました。
江戸時代の日本は300の独立主権国家の連合体だったわけです。
加藤さんによれば「民主党は全国を300の広域連合自治体を
中心とした分権化を進める方針を出している」そうです。
これですとちょうど江戸時代の藩の数と同じになりますね。
私としては、なるべく旧藩の領域に合わせるように300にするのが
良いプランだと思います。地域の一体感という点で歴史的にもっとも
無理がない形だと思うのです。
最近の広域合併で、わけのわからない怪しげな地名も誕生していますが、
旧藩を復活させて、その名称に戻してしまうのが歴史的に無理がないように思えます。
もちろん加賀や薩摩や土佐のように、旧藩の大きさがちょうど現在の県の大きさに
等しいという地域もあるのですが、それはそれで良いのではないかと思います。
藩は自然の流域や地形に規定されたまとまりを単位としているので、
大きい藩もあれば小さい藩もあるのは仕方ないことです。
広い平野を擁する藩は大きくなってしまいますし、
小さい盆地や谷筋の藩は小さくなってしまいます。
しかし、それが自然の地形に規定された地域のまとまりだから仕方ない。
もちろん江戸時代の旧藩にも、幕府の策略で地理的にかなり
無理な線引きがされているものもありますから、
そうしたものはより自然のまとまりに修正する必要があります。
信濃の場合、江戸時代は11の小藩に分かれていました。
自然の地形に応じて盆地ごとに藩がある感じで、
盆地と盆地のあいだに山があってつながっていないので、
どうしても小藩に分かれざるを得なかったのです。
信濃では、最大が真田家・松代藩で10万石、
次いで松本藩の6万石、三番目が上田藩の5万3000石・・・・となります。
小さな藩ばかりでした。それぞれの盆地にそれだけの生産力しかないから
仕方なかったわけです。
そして今でも信州人は、盆地ごとに文化的な違いがあり、お互いに仲も悪いのです。
「道州制」というのは、私には何故必要なのかよく分かりません。
藩の上にくる統治単位は国でよいのであって、
道とか州とかいった名称の中間的統治単位が何故必要なのか疑問に思います。
もちろん藩と藩のあいだには大きさや工場の立地などに
応じて貧富の格差が生じるでしょうから、広域的に再分配を行う必要があります。
しかし、それは国がやればよいのであって、道とか州という単位は必要なのでしょうか。
道・州がどのような機能を果たすのか、イマイチよく分からないのです。
藩を自治の基礎として、さらに「信濃」というアルプスの山々に囲まれた地理的まとまりの
概念が共有されていればよいのではないかと私は思います。
道州制にあわせて「信濃」という概念が抹殺されてしまうような事態には私は断固として反対です。
加藤さんも、道州制の導入は新たな辺境を生み出すだけだと批判していましたが、同感です。
伊那谷の人々は、明治維新によって「長野県」という行政単位が導入されたことにより、
辺境の地位に押しやられてしまったという不満がかなりあるようです。
何せ、長野に行くよりも名古屋に行く方が早いという場所ですから。
しかし、伊那谷が名古屋圏に入ったとしても、
やはり名古屋圏の中の辺境として扱われるだけだし、
辺境として扱われる地域は今よりも増えてしまうだろう、というのが加藤さんの懸念でした。
私も同感です。
道や州は自治の基本単位としては大きすぎ、
「辺境」の地位で疎外された地域が多く出るでしょう。
藩の大きさならば、顔の見える範囲の自治が実現し、
誰もが主役になれ、地域は活性化すると思います。}}
植草一秀(うえくさ かずひで)氏のブログより
{{日本の国会議員数は、人口比で見ると、諸外国と比べて多すぎるものではない。
政府支出の削減という観点から見れば、削減するべきは国会議員定数ではなく、
地方議員定数である。
現在日本には1789の地方公共団体があり、
39,255人の議員定数と首長が存在する。
かつての3000団体から見れば約半分になったが、まだまだ多い。
日本の地方公共団体を、人口40万人を目安に300団体に再編し、
この300団体を基礎自治体とする。
基礎自治体には極めて強い自治権を付与する。
江戸時代の「藩」を復活させるわけだ。
つまり「廃県置藩」を断行するのだ。
この300の基礎自治体が20名定員の議会を持つなら、
議員定数と首長の合計は6300人になる。
各団体が30名定員の議会を持つなら合計数は9300人だ。
いずれにしても、現在の約4万人と比較すれば、4分の1ないし、
6分の1に人数を減らすことができる。
政府支出のスリム化を掲げるなら、この程度の抜本改革を行うべきだ}}
南里 俊策氏(大分合同新聞)のブログより
{{寺子屋、藩校、廃県置藩のすすめ
教育に力を入れたがために滅びてしまったという国が歴史上、
この地球にあったかどうか、その方面に疎い私には分からない。
ただ、十九世紀にアジアの国々が次々に欧米の植民地になる中で
日本だけはならなかった。
なぜか。その背景はいろいろあるが、その一つとして誰もが認めるのは
日本の教育水準の高さである。
例えば、識字率や就学率。江戸はそれが八割から九割に達していた。
同時代のヨーロッパ、もっとも進んでいたイギリスの都市で二割台、
フランスにいたっては一割にも到ってなかったという。
江戸の町は寺子屋だらけ、そこに六歳から八歳ぐらいの子が通って学んだ。
読み書き、そろばんの手習い、少し程度が高くなると、四書五経、漢詩の素読など
和漢の古典を叩き込んだ。
だれも「詰め込み教育反対」「ゆとり教育を」など気の利いたいた口を叩くものはいなかった。
強制、詰め込みこそが学力の原点であることを知っていたからである。
今の日本人はそこを勘違いしている。
こうした教育事情は地方でも同じである。
各藩は厳しい財政の中で藩校をたて、塾をつくった。
人材養成こそ苦境脱出の手がかりであると考えたからだ。
今のように「中央政府(幕府)はもっと教育予算を増やせ」と叫んでもビタ一文出るはずはない。
米百俵の精神で自分でやる以外にはない。
世界でもトップの日本の教育水準の高さは、こうした地域、地方の自立自存の素地の中から生まれた。
まさに地方分権である。
義務教育に反対するわけではないが、廃藩置県で教育は国の責任で行うものだと
みんなが考えるようになって,教育はおかしくなったのではないか。
全国画一的な教育ではなく、おれたちの町、あたしたちの村の子どもはこういうように育てたい、
そんなイメージを作ることだ。
町は貧しいけれど、何はともあれ教育だけにはカネを出そう、そんな町があってもいい。
またその反対の町もがあっても仕方ない。
住民が決めること。
年寄りは遅かれ早かれいずれ死ぬ。
町の明日、ひいては国の未来を担うのは子どもたち。
ひ弱な育て方をしてはいけない。
それには、読み書き、算数を徹底的に叩き込んで基礎学力作り。
あの藤原正彦先生も言っているではないか、一に国語、二に国語、三四がなくて五に算数と。
小学校ではこれだけやれば十分。
後はのびのびと体力作り。
うちの町の学校では、これ一本でやりますと、町長なり教育長が考えてもそれは出来ない。
霞ヶ関の役人たちが作ったこまごまとしたメニューウに従わなければならないからだ。
江戸時代に培われた地域の教育力を奪ったのは、廃藩置県による教育の国家統制である。
結論は出た。
教育の再生を図るには、廃藩置県を廃止し、新たな廃県置藩を断行、
地域の教育力を甦らせることだ。}}
荒木村重と名乗る人のブログより
{{廃藩置県からちょうど140年を経たの
中央集権が完全に制度疲労を起こしておる
そろそろ逆に回さねばならぬ
廃県置藩でもないが
人財も金財も権限も一極集中を止め
地域に分散せねばもうもたぬ
方言お祭り名物がどんどん溢れる
個性豊かな地方の地点を増やさねばならぬ}}
Posted by 古恵良 元 (こえら はじめ) at 15:27│Comments(0)